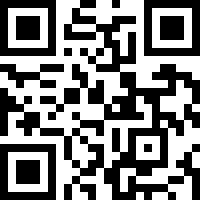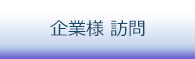ストレッチは30秒以上続けないと効果がない?科学的根拠を解説
患者さんによく「ストレッチは何秒くらい持続すればいいですか?」と質問されます。
この記事ではストレッチの持続時間に関する興味深い研究結果をご紹介します。
ストレッチの効果と持続時間の関係
ストレッチは、筋肉の柔軟性を高め、関節の可動域を広げるために非常に有効です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、適切な時間ストレッチを続けることが重要です。
ある研究によると、結論ストレッチは30秒以上持続して行うことで、筋肉の柔軟性が向上し、効果がでることが明らかになりました。
これを聞くと「30秒!?長っ!」と思う方も多いでしょう。
逆に言うと短時間のストレッチでは、効果は限定的であまり変化が起きないということです。
なぜ30秒以上必要なのか?
筋肉は、伸ばされると「筋紡錘」というセンサーが反応し、伸びすぎを防ぐために収縮しようとします。この反応を「伸張反射」と呼びます。ストレッチを30秒以上続けると、この伸張反射が次第に弱まり、筋肉がリラックスしてより深く伸びるようになります。
30秒以上のストレッチを行うことで、伸ばすことによる感じる軽い痛みに対して耐性が高まり、筋肉柔軟性や可動域が向上しやすくなるのです。
研究結果の具体例
具体的な研究では、以下のような結果が報告されています:
大規模な人数での研究では、30秒以上のストレッチを行ったグループと15秒以下の短時間のストレッチを行ったグループを比較すると柔軟性の向上に明確な差がうまれたようです。
この結果から、ストレッチを行う際には、少なくとも30秒以上続けることが推奨されています。
またご高齢の方を除き、1分以上ストレッチをしても効果は30秒以上のストレッチの効果と差がないこともわかっています。
当院でのストレッチのアドバイス
ストレッチにはこれだけやれば間違いないといったことや、これが正解というような答えがあるわけではありません。あくまで上記のような研究エビデンスをふまえて、患者さんに以下のようなストレッチのポイントをお伝えしています。
1. 30秒以上続ける
各ストレッチを30秒以上持続し、筋肉をしっかりと伸ばしましょう。
2. 呼吸を意識する
ストレッチ中は深くゆっくりと呼吸をし、リラックスすることが大切です。
3. 無理をしない
研究結果では痛みを感じるくらいの強いストレッチのほうが効果があったとされるエビデンスもあります。ですが、不調のある方ですと逆に痛めてしまったり、最大限の効果を期待するほどのストレッチができない状態の方も多いため、強い痛みを感じるほど強く伸ばすことなく、適度な張力(筋肉にかかるテンション)を感じる範囲で行うようにアドバイスしてます。
また、とにかく継続してストレッチをする習慣の力が最も大事なことをお伝えします。
まとめ
ストレッチは、30秒以上続けることで効果が高まることが科学的に証明されています。ぜひ、日々のストレッチにこの知識を取り入れて、より効果的なケアを実践してください。
ストレッチに限らず、最新文献なども積極的に目を通して、科学的なエビデンスを基にした情報を分かりやすく伝えることで、患者さんの理解が深まり、ストレッチの効果を最大限に引き出すことができます。
患者さん一人ひとりに合ったストレッチ方法をアドバイスしています。
お気軽にご相談ください。
整体・legitの公式LINEアカウントがあります。
LINEでご予約も承ります。
もしよろしければで、ID検索またはQRコードからご登録ください。
ID : legit-seitai
メッセージは24時間受け付けますが、返信をすぐできない場合もございます。
お急ぎの方は直接お電話ください。
また、急なキャンセル等もLINEではなく、お電話いただけると幸いです。
宜しくお願いします。
整体・カイロプラクティック legit - 国分寺 -
☎042-312-4707
股関節痛でお悩みの方へ。
股関節は私たちの体を支える重要な関節ですが、痛みが生じると日常生活に大きな影響を与えます。この記事では、解剖学や組織の働きについて詳しくない方でも理解できるよう、股関節痛の原因をわかりやすく説明します。整体院として、予防や改善のヒントもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
股関節とは?
股関節は、骨盤と大腿骨(太ももの骨)をつなぐ関節です。体の重さを支え、歩行や立ち上がり、座るなどの動作に欠かせない役割を果たしています。股関節は「球関節」と呼ばれるタイプで、前後左右に広く動かすことができるのが特徴です。
股関節痛が起こる主な原因
股関節痛の原因はさまざまですが、以下のような要因が考えられます。
加齢による変形性股関節症
加齢に伴い、股関節の軟骨がすり減ることがあります。軟骨は関節の動きを滑らかにするクッションのような役割を果たしていますが、すり減ると骨同士が直接ぶつかり、痛みが生じます。これが「変形性股関節症」です。特に高齢者に多いですが、若い方でも姿勢の悪さや過度の負担が原因で発症することがあります。
また、生まれつき球関節のはまりが浅かったり、逆に隙間が少なかったりと先天的な要因で痛むこともあります。
筋肉の緊張や疲労
股関節周辺の筋肉(お尻や太ももの筋肉)が緊張したり、疲労がたまると、股関節に負担がかかります。長時間の立ち仕事や運動不足、不良姿勢などが原因で筋肉が硬くなり、痛みを引き起こすことがあります。
股関節の炎症
股関節に炎症が起こると、痛みや腫れが生じます。炎症の原因としては、関節リウマチや感染症、過度の運動などが挙げられます。特にリウマチは免疫系の異常によって関節が攻撃される病気で、股関節にも影響を及ぼすことがあります。
骨盤の歪み
骨盤が歪むと、股関節への負担が不均等になります。片側に体重がかかりすぎると、関節や筋肉に過度のストレスがかかり、痛みが生じることがあります。骨盤の歪みは、長時間のデスクワークや姿勢の悪さ、出産後のケア不足などが原因で起こりやすいです。
外傷やケガ
転倒やスポーツ中のケガで股関節を痛めることもあります。骨折や脱臼、靭帯の損傷などが原因で、痛みが長引くことがあります。
股関節痛を予防・改善のヒント
股関節痛を予防・改善するためには、以下のポイントを意識しましょう。
適度な運動で筋肉をほぐす
股関節周辺の筋肉を柔らかく保つことが大切です。ストレッチや軽い運動を習慣化し、筋肉の緊張をほぐしましょう。特に太ももやお尻のストレッチは効果的です。
正しい姿勢を心がける
姿勢が悪いと、股関節に余計な負担がかかります。立つときも座るときも、背筋を伸ばし、骨盤を立てるように意識しましょう。デスクワークの方は、定期的に立ち上がって体を動かすことも重要です。
体重管理をする
体重が増えると、股関節への負担も大きくなります。適正体重を維持するために、バランスの良い食事と適度な運動を心がけましょう。
整体で骨盤の歪みを調整
骨盤の歪みが気になる方は、整体で調整することをおすすめします。整体では、骨盤の位置を整え、股関節への負担を軽減する施術を行います。定期的に通うことで、痛みの予防にもつながります。
痛みが強い場合は早めに受診
股関節痛が強い場合や長引く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。特に変形性股関節症やリウマチが疑われる場合は、適切な治療が必要です。
まとめ
股関節痛は、加齢や筋肉の緊張、骨盤の歪みなどさまざまな原因で起こります。股関節は可動域が広い分、絶妙なバランスで成り立っているため、痛みが出やすい関節でもあります。
日常生活での姿勢や運動習慣、ストレッチや運動といった月並みなアドバイスではなかなか良くならないのも現実問題としてあります。
股関節痛でお悩みの方は、どういった原因から痛みが出ているのか、どんなことをしたら良くなるのかを、それぞれの患者さんに合わせたアプローチ、アドバイスをしますので、ぜひ一度ご相談ください。