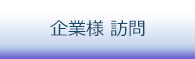脳の重さは体重の約2~3%ほどですが、エネルギーの消費量は全身の20%ほどを占めるのをご存知ですか?
脳は視覚や聴覚からの情報や、何かを考えたり、感じたりするのに働いていますし、それ以外にも全身の筋肉や内臓機能にも司令を出したりと、常に大量のエネルギーが必要になります。
脳のエネルギー源はブドウ糖
筋肉を動かすにはブドウ糖以外に脂質もエネルギー源となりますが、脳はブドウ糖しか使えません。
また、ブドウ糖を燃やしてエネルギーにするときに酸素が必ず必要になります。
血糖値が下がり過ぎると脳が活動できなくなってしまいますから、肝臓などに蓄えられたブドウ糖を放出し、血糖値を保つようなしくみが体には備わっているわけです。
朝ごはんは脳のためにも重要!?
そもそもなんで脳のエネルギー源の話をしたかというと、患者さんで朝が弱くて何も食べない方が、午前中は職場で頭が働かず、ぼーっとあくびばかりしてるとおっしゃっていたので、脳へのエネルギー供給が不十分だからではないか?と話したからです。
朝からがんばってスイッチを入れようとしても、エネルギーが不足していては気持ちだけでは無理なわけです。
あくびが沢山出てしまうのも、脳の軽い酸欠状態のときに頻発する場合があります。
子供の頃に早寝早起きが大事だとか、朝ごはんしっかり食べて学校に行きなさいとか、うるさく言われた方もいるかもしれませんが、間違いないアドバイスかと思います。
朝起きたら、窓を大きく開けて空気を入れ換えて、しっかり酸素を身体に取り込んで、栄養のある食事をしてエネルギー源を蓄える。
活発に活動を始めることで脳や全身の血流も良くなり、充実した一日を過ごせるわけです。
やっぱり食事は大事です。(^^

日本食生活協会の「食生活ガイドブック」に生活習慣病を防ぐために実践したい食生活指針として、10個の項目を挙げています。
参考までにご紹介します。
皆さんはいくつ当てはまるでしょうか?
食生活指針10項目
1. 食事を楽しみましょう。
・心と体においしい食事を、味わって食べましょう。
2. 1日の食事リズムから健やかな生活リズムを。
・朝食で、いきいきとした1日を始めましょう。
3. 主食、主菜、副菜を基本に、食事バランスを。
・手作りと外食や加工食品・調理食品を上手に組み合わせましょう。
4. ご飯などの穀類をしっかりと。
・日本の気候・風土に適している米などの穀類を利用しましょう。
5. 野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。
・たっぷりの野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維を摂りましょう。
6. 食塩や脂肪は控えめに。
・塩辛い食品を控えめに、食塩は1日8g~10g未満にしましょう。
7. 適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を。
・普段から意識して体を動かすようにしましょう。
8. 食文化や地域の産物を活かし、時には新しい料理も。
・地域の産物や旬の素材を使うとともに、行事食を取り入れながら、自然の恵みや四季の変化を楽しみましょう。
9. 調理や保存を上手にして、無駄や廃棄を少なく。
・賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。
10. 自分の食生活を見直しましょう。
・自分の健康目標を立て、食生活を点検する習慣を持ちましょう。
食生活の乱れは仕事やライフスタイル、人間関係、ストレスなど、様々な生活習慣に必ず原因があります。
上記の10項目はよく言われていることばかりですが、生活習慣病にならないためにも、これならできるなと思うものから、少しずつ実践していくのはいかがでしょうか?
食の秋(^^)暴飲暴食は注意ですね◎

ホームセンターで木材を買ってきて、植物を置くラダーラックを作りました。

労力と時間を考えると買った方がいいかなぁとも思いましたが、イメージしているものを探すのも大変ですし、自分たちで作ったほうが良いものができる気がしたのでやってみました。
イメージ通りに仕上がったので満足しています。

低めの2段のラック

腰の高さくらいの3段ラック
木材がまだあまっているので、もう一つくらい何か作ろうと検討中です。
過ごしやすい気温なってきましたね。
私の好きな季節がやってきました(^^
季節の変わり目、体調を崩さないように皆さんご自愛ください。